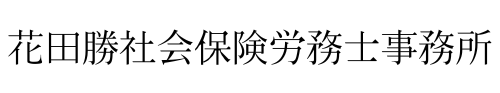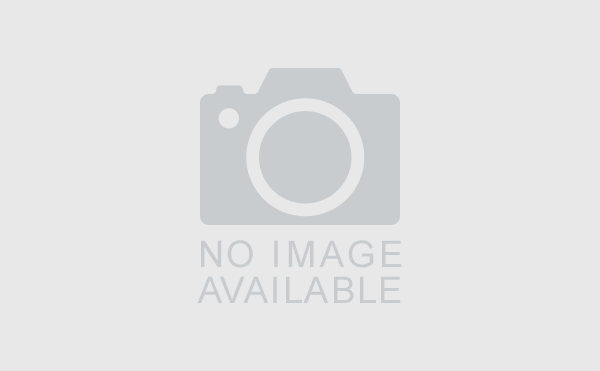退職時のデータ削除で損害賠償?徳島地裁判決に学ぶ“やってはいけない退職行動”
退職間際、会社のパソコンに残る自分の資料を整理しようと考える人は多いものです。でも…その“整理”、もしかしたら損害賠償リスクになるかもしれません。
2025年1月、徳島地方裁判所で、退職者が削除した業務データについて企業側が損害賠償を請求し、約577万円の支払いを命じる判決が出されました。この記事ではその判決の概要と、企業がとるべき予防策についてわかりやすく解説します。
🧾 判決の概要(令和7年1月16日・徳島地裁)
この判決は、企業のサーバー上のフォルダを退職当日に削除した元従業員と、その身元保証人に対して損害賠償が命じられたというものです。
- 削除対象:研究開発関連のファイル232フォルダ
- 削除方法:自動削除プログラムを仕込んで、退職当日に起動
- 損害額:再構築にかかる人件費や復旧作業の費用として約577万円
- 判決:「不法行為」にあたるとして、元従業員と保証人に損害賠償を命令
⚠️ 企業にとってのリスクと教訓
今回のケースは「故意」による削除でしたが、次のような“よかれと思って”の行動でもトラブルにつながるおそれがあります。
- 自分が作成したデータを個人PCにコピーして削除
- 引継ぎのつもりで古いデータを一括削除
- 私用データと一緒に業務ファイルも誤って削除
こうした行為が「業務上必要なデータの喪失」につながった場合、使用者側の損害が大きければ損害賠償の対象になることもあり得ます。
✅ 企業ができる実務対策リスト
退職時のトラブルを防ぐために、次のようなルール整備・運用がおすすめです。
1. データのバックアップ体制を整備
- 定期的な自動バックアップの実施
- 退職日直前の「全社的なバックアップ日」の設定も効果的
2. アカウント・端末の管理強化
- 退職日当日にログイン不可とする手続きの整備
- 私物USBや外部ストレージの接続制限設定
3. 就業規則や誓約書での明文化
- 「退職時に会社資産(データ含む)を削除してはならない」旨を記載
- 秘密保持や損害賠償に関する誓約書も有効
4. 引継ぎ資料の標準化
- どのデータを、どのフォルダに残すかを引継ぎチェックリストで明確化
📌 まとめ
今回の徳島地裁判決は、退職時の不用意なデータ削除が重大な法的責任を招くことを示した実例です。
退職時は「お互いに気持ちよく終える」ことが大前提ですが、その裏側で企業が失ってしまう情報資産が、金銭的にも精神的にも大きな損害になりかねません。
人材と一緒に、会社の“知的資産”もきちんと引き継ぐ体制づくり。それが今、企業に求められる情報管理です。
花田勝社会保険労務士事務所(所在地:東京都足立区)では、北千住をはじめとした東京・千葉・埼玉・神奈川・茨城等の中小企業の皆さまに向けて、労務相談や雇用・社会保険の各種手続き、給与計算、就業規則の見直しなど、幅広いサポートを行っております。
📩 お気軽に👉️お問い合わせください。
また、LINE公式アカウントでもご相談お待ちしておりますので、QRコードからぜひご登録ください。